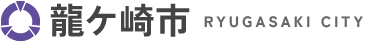コミュニティ・スクールとは
「学校運営協議会」(地教行法第47条の5)が設置された学校のことです。
地域と学校が一体となって、子どもたちの成長を支えます。
龍ケ崎市でも、小中学校と地域が一体となって子どもたちの豊かな成長を支える「地域とともにある学校づくり」を進めていくために、コミュニティ・スクールを導入することになりました。
令和6年度は、馴柴小学校がモデル校として取り組みました。令和7年度は中根台中学校に学校運営協議会を設置します。
コミュニティ・スクールの効果
子どもたちの健全育成を確保し、「地域の担い手を育てていく」とともに、地域の方が学校教育活動へ携わり、学校や地域の課題を解決していく「大人の学び」が充実します。
そのため、「地域の教育力」「学校と地域の活性化」が期待できます。
コミュニティ・スクールの仕組み
教育委員会より委嘱された協議会の委員が年に数回、熟議(熟慮と議論)をします。
よりよい集団(学校)生活や人間関係を築くために、協働して取り組む一連の自主的、実践的な活動を話合いを重ねながら進めていきます。
学校運営協議会とは
「学校運営協議会」は、保護者や地域の代表・教職員などで構成された組織です。
「子どもたちにどう育ってほしいか」を話し合う場になります。
教育の目的などを共有し、子どもたちに必要な支援や教育活動の質の向上などについて、地域と学校が当事者意識を共有しながら一緒に考えます。
令和6年度モデル校 馴柴小学校の取り組み
コミュニティ・スクールの設置にあたっては、馴柴小学校をモデル校として取り組みました。学校長が作成する学校運営の基本方針の説明の後、学校・保護者・地域の代表による委員の皆さんで話し合いが行われ、承認されました。3回行われた協議会の中では、学校の教育目標を実現するために、学校と地域が一緒に子どもたちを育てていくことを中心に話し合いを行いました。また、学校評価アンケートに関する意見交換などが行われ、地域でできる学校支援に向けての話し合いも行われました。
第1回目の様子

第2回目の様子

第3回目の様子
![]() 令和6年度 馴柴小学校学校運営協議会 議事概要(PDF:223KB)
令和6年度 馴柴小学校学校運営協議会 議事概要(PDF:223KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ