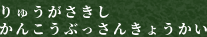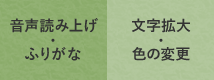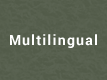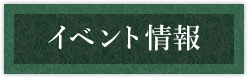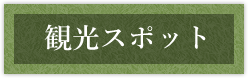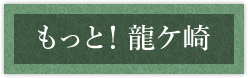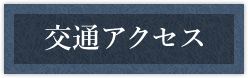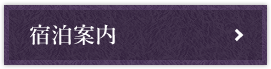龍泉寺=りゅうせんじ(下町)

龍泉寺(東福山水天院)は、龍ケ崎地区のほぼ中央、下町にある天台宗の寺で、一般には「龍ケ崎観音」の呼び名で親しまれています。
天正年間(1573~1592年)、江戸崎城主・土岐胤倫(後に龍ケ崎城主)の創建と伝えられ、寛永年間中(1624~1644年)上野寛永寺の天海僧正が再興しました。
明治のはじめに10余年の歳月をかけて本堂を再建しましたが、その落成寸前に龍ケ崎の大火で消失。
長らく仮本堂でしたが、昭和50年に新築され、現在に至っています。
胤倫が妻・お福の方の難産に際し、山城国から弘法大師の作とされる正観世音菩薩の尊像を迎えて寺を建て祈願したところ、無事出産できたという伝えがあり、今も安産・子育て・出生・開運・除災の観音様として広く信仰を集めています。
本尊は安産祈願のため淳和天皇の勅を受けた弘法大師の作という聖観世音菩薩で、「安産観音」として有名です。
水子地蔵は約200体とも言われています。
また龍泉寺では、絵馬を参拝者に配り、参拝者はそれに自分の願い事を書いて祈願します。
安産を祈願する人には安産のお守り、腹帯守、ろうそく、餅、米を授けています。
餅は紅白のどちらかで、白ならば男の子、赤ならば女の子が生まれるとされ、不思議とよく当たると評判です。
ろうそくは、これが消えるまでにお産が早く済むことを願って、短いものが授けられます。
毎月17日が縁日で、特に正月17日(現在は15日)は近隣からの参詣客でにぎわいます。
また7月10日の「ほおづき市」は、4万6千日分の参拝をしたことになる功徳日で、お参りをしてほおづきを求める人が数多く詰めかけます。
問い合わせ先
電話:0297-62-2373
「龍泉寺(龍ケ崎観音)」公式サイト